![]() こちらもご覧ください!(広告掲載のご案内)
こちらもご覧ください!(広告掲載のご案内)
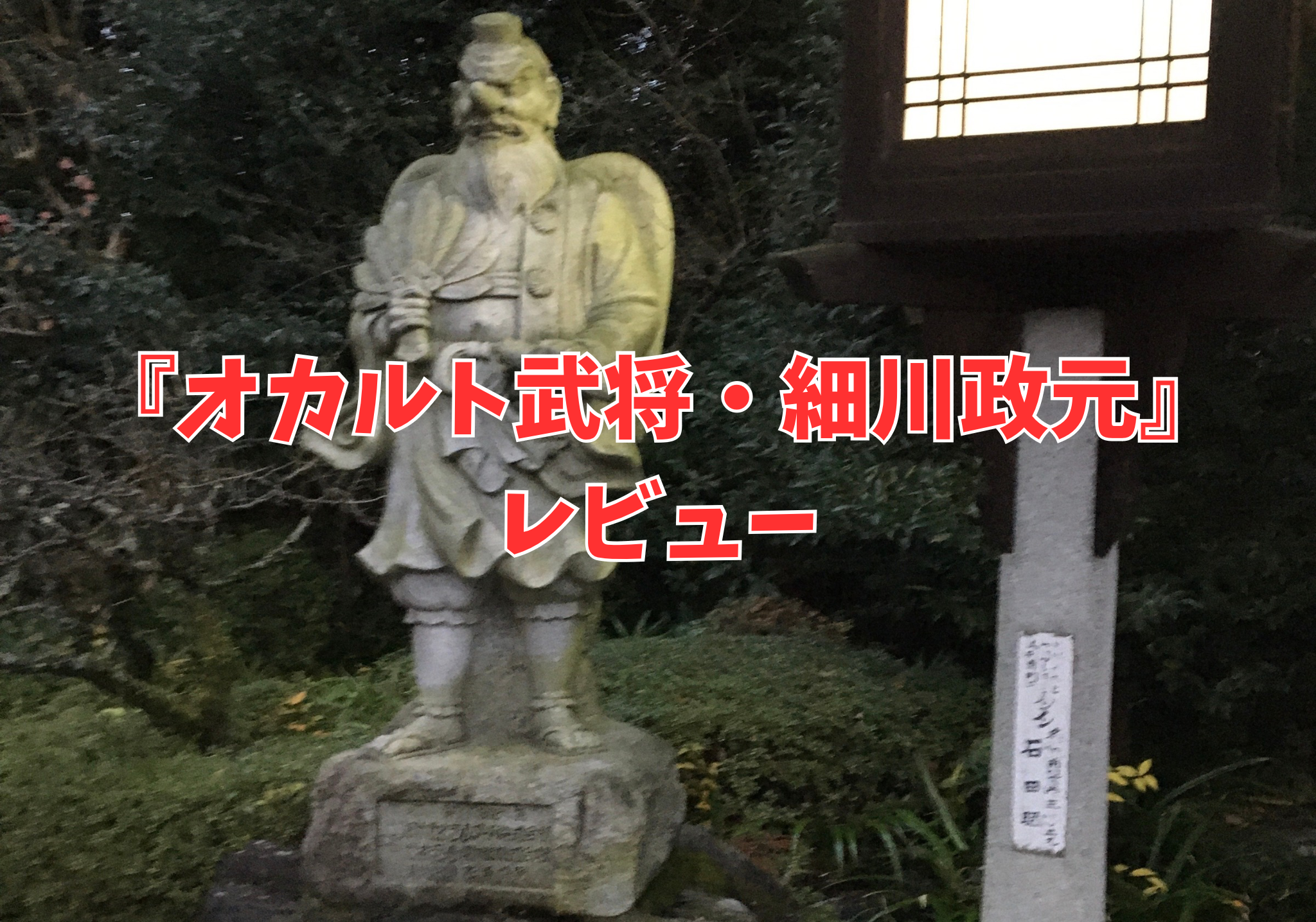
思い立ったが吉日! こんにちは、toproadです。
今回は『オカルト武将・細川政元』を読みましたので、そのレビューを書きたいと思います。
のちのち、AIがすばらしいレビューを書くかもしれませんが、自分の中でいろいろ気づきがあったので書いていきます。
僕は戦国時代には興味があるのですが、応仁の乱とか、明応の政変とか、細川氏が権力を持った時代の頃は人物の相関図が複雑すぎて正直、理解しきれていません。
なので、京周辺における戦国時代の始まりについての知識は乏しいです。
ちなみに関東の室町時代後期から戦国時代初期の情勢についても同じで理解しきれていません。
そんな中で細川政元が「天狗になりたくて修行に明け暮れた」とか、「修行のために子供(跡取り)がいなかった」という人であることは知っていました。
なので、「細川政元とはどんな人か?」を知りたくてこの本を読みました。
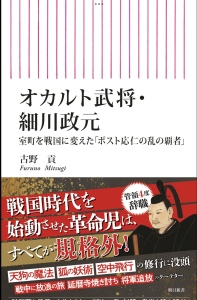
細川政元とは?
以下、wikipediaより引用です。
細川 政元(ほそかわ まさもと)は、室町時代後期から戦国時代初期の武将、守護大名。室町幕府24、26、27、28代管領。摂津国・丹波国・土佐国・讃岐国守護(一時的に近江国守護も)。細川家宗家(京兆家)12代当主。養子に澄之、澄元、高国がいる。
日野富子や伊勢貞宗らとともに10代将軍・足利義材を追放して、11代将軍・義澄を擁立し(明応の政変)、管領として幕政を牛耳り(京兆専制)、比叡山焼き討ちを行ったり、畿内周辺にも出兵するなど、細川京兆家の全盛期を築き、当時日本での最大勢力に広げた。政元は幕府の実権を掌握し、事実上の最高権力者になり、「半将軍」とも呼ばれた。
だが、3人の養子を迎えたことで家督争いが生じ、自らもその争いに巻き込まれる形で家臣に暗殺された(永正の錯乱)。応仁の乱の混乱の後、実力者政元の登場によって小康状態にあった京・畿内周辺は、その死と澄元・高国両派の争いによって再び長期混迷していくこととなる。
修験道に没頭して女性を近づけず、独身を貫いたため、実子はいなかった。
以下は補足です。
1466(文正元年)、応仁の乱の東軍の大将、細川勝元と西軍の大将、山名宗全の養女との間に産まれる。
1473年(文明5年)、細川勝元が亡くなり、8歳で家督を継ぐ。分家の典厩家の細川政国や領国の守護代クラスで構成される「内衆」の補佐を受ける。
1474年(文明6年)応仁の乱終結。
1479年(文明11年)細川家の家臣同士の争いのために拉致される。
1487年(長享元年)鈎の陣に参加。
1489年(延徳元年)足利義尚、鈎の陣の最中に病死。
1491年(延徳3年)摂関家の九条政基の次男を養子とする(澄之)。
1493年(明応2年)明応の政変。足利義材が畠山義豊討伐で出兵したタイミングでクーデターを実行。足利義澄を将軍に擁立。将軍を傀儡化して、細川政元が幕政を握る「京兆専制」を確立する。
1499年(明応8年)越中国へ逃亡していた足利義材の上洛の味方をした比叡山延暦寺を焼き討ち。
1503年(文亀3年)細川阿波守護家より養子を取る(澄元)。
1507年(永正4年)永正の錯乱。入浴中に暗殺される。享年41。
養子を取ったことによって細川家の家督争いが起こり、暗殺されています。
ちなみに、明応の政変をきっかけとして、将軍が京から逃げる事例が増えます。
その詳細が以下の動画で解説されています。
どんな点が「オカルト」なのか?
タイトルにもある「オカルト」ですが、細川政元のどんな行動がそう思われたのでしょうか?
- 修験道に傾倒し、鞍馬山で修行をする
- 安芸国の司箭(しせん。宍戸家俊(ししど いえとし))という山伏を京に呼んで、一緒にお経を読んだり、兵法を学んだり、酒を飲んだりした
- 北陸へ出かける時に山伏の格好をしていた
- 相手を呪う「呪詛」のお経を読んでいた
- 天狗に憧れて修行をした
- 修行の妨げになるとして、女性を寄せつけなかった
- 烏帽子をかぶるのが当たり前の時代に烏帽子をかぶることを拒否して、自分の擁立した足利義澄の将軍宣下が1週間延期になった
この本においてはオカルトに走った理由について、
- 細川家の当主の立場なのに自分の思う通りに動くことができなかったから
- 「得体の知れない術」を使うと思わせることで自分に従わせようとした
- 山伏が自由に行動できた点を利用しようとした
と、しています。
僕としてはやはり、山伏が比較的自由に全国を移動できたということが細川政元が修験道に傾倒した理由だと感じました。

ネットワーク構築と実利主義
室町時代当時の考え方では「オカルト」と周りから捉えられた細川政元の行動ですが、僕は彼なりの考えがあっての行動だったと感じました。
京にいてなかなか自由に地方に行けない時に地方の情報を得るために、少しでも自分が自由に動きやすくするために、修験道を利用してネットワークを構築しようとした。安芸国から司箭を呼んだことも西の情報を得るためではないか。
修験道で山に入って自分の感覚的な部分を鍛えたり、自然と向き合うことで権威とか儀式みたいなものが意味のない、ムダなものに感じるようになった。
そうして実権のない将軍に意味がないと考えたり、名前だけの管領になっても意味がないと思って何回も数日で辞任したり、烏帽子をかぶるのを拒否したりした。
そして、実利主義的なところが儀礼や儀式、権威や宗教的なものを重くみていた当時の考え方とは相容れなかったので、「オカルト」と言われたのかなと思います。

三好長慶、織田信長以前の先駆者
将軍を自らの意思で擁立したということがのちの三好長慶や織田信長の将軍に対するスタンスにつながっていきます。
三好長慶や織田信長以前に「半将軍」と呼ばれるほどの権勢を誇ったのも細川政元です。
また、この本を読んで強く感じたのは織田信長に強く影響を与えているのではないか? ということです。
織田信長が「うつけ」と呼ばれるような振る舞いを見せていたのも実利主義からくるものではないか? と僕は思っています。
当時のしきたりと振る舞いが合わずに「うつけ」と思われていたということではないか。
将軍の上洛に協力するが、自分に利益がなくなると追放、形式的な官位には興味を持たない、という姿勢も細川政元と重なるところがあります。
そして、比叡山焼き討ち。これも織田信長が細川政元の影響を受けたものでは? と思ってしまいます。
両者ともに、たまたま延暦寺と対立したから、ということなのかもしれないですが。

まとめ
細川政元は今川氏真、大内義隆とともに「戦国三大愚人」とされていますが、あくまで「戦国武将=いくさに強いのが正義」というイメージによるものだと思います。
むしろ、織田信長に多大な影響を与えた人物で、愚人ではないでしょう。
僕は織田信長は自分以前のいろいろな要素を取り入れて行動していたと考えていますが、また新たなサンプルを認識できました。
このレビューを読んで「おもしろそうな本だ」と思われた方はぜひ『オカルト武将・細川政元』を読んでみてください。
ここまで読んでいただいてありがとうございました。今回は以上です。
![オカルト武将・細川政元 室町を戦国に変えた「ポスト応仁の乱の覇者」 (朝日新書)[新書] - 攻城団](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/P/4022953144.09.LZZZZZZZ.jpg)